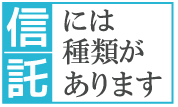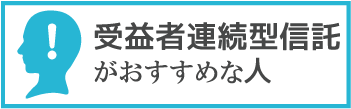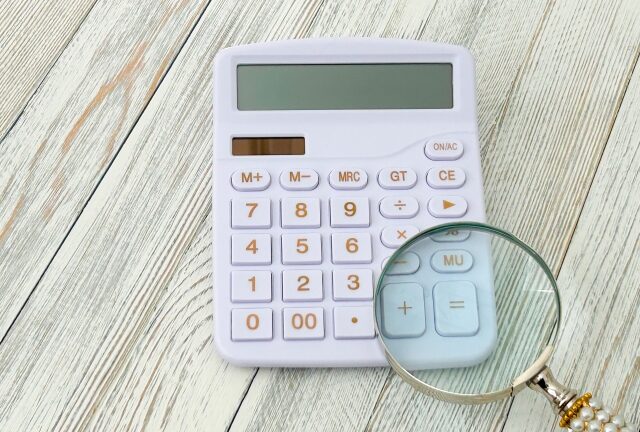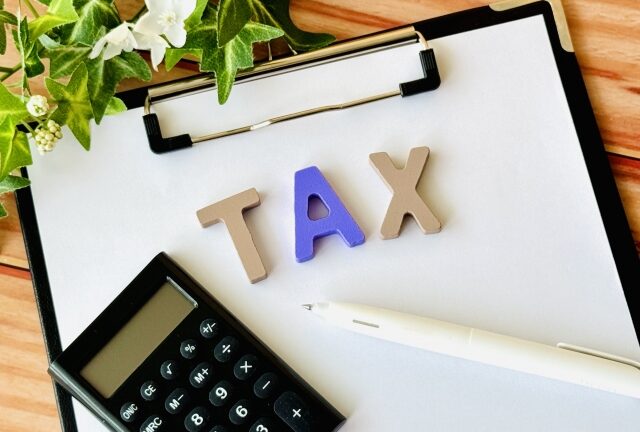相続発生後、残された配偶者の生活において「住まいの確保」は最も重要な課題のひとつです。これまでの制度では、配偶者が自宅の所有権を取得しなければ居住を継続できず、結果的に他の財産を受け取れないケースが少なくありませんでした。こうした問題を解決するために創設されたのが「配偶者居住権」です。
本記事では、この制度の概要や成立要件、存続期間、そして注意すべきポイントについて詳しく解説します。
配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、夫または妻が亡くなったあとに、残された配偶者(法律上の配偶者)が、亡くなった配偶者名義(あるいは共有名義)であった居住用建物に、終身または一定期間、無償で住み続ける(使用・収益する)ことができる制度です。
この制度が登場した背景には、従来、配偶者が亡くなったあと残された住居から転居を余儀なくされたり、所有権を取得すると他の財産を十分に確保できなくなったりというケースがあったため、配偶者の住居確保を法的に保護する必要があったという事情があります。
施行時期としては、相続法の改正に伴い、2020年4月1日以降に開始する相続から適用可能とされています。
該当する対象
配偶者居住権が該当する対象者は、次の通りです。
- 対象となる人…配偶者(戸籍上の婚姻関係にある夫または妻)。内縁・事実婚の配偶者は原則対象外です。
- 対象となる建物…被相続人(亡くなった方)が単独で所有、または配偶者と共同所有していた建物で、配偶者が相続開始時点でその建物に居住していたことが要件です。
このように、「住み慣れた家を手放したくない」「住居確保と老後の生活資金確保を両立したい」といった配偶者の立場に配慮された制度といえます。
なぜこの制度が必要だったか
この制度が導入されたのは、さまざまな理由があります。
まず、相続財産の中に居住用不動産(建物・敷地利用権)が多くを占める場合、配偶者がその建物を取得するためには、その価額分を相続分として取得することになり、預貯金その他の流動資産がほとんど残らないという事態が生じていました。
また、建物を所有権として取得せず賃貸する形になると、毎月の賃料支払い負担などが老後の生活を圧迫する恐れがありました。 さらに、所有者の事情で建物が売却されたり転貸されたりすると、配偶者が住み続けられなくなるリスクもあり、無保障な住居生活を余儀なくされる場合もありました。
こうした問題を受けて、法律(改正民法)によって配偶者居住権・配偶者短期居住権という枠が新設され、配偶者の居住を法的に保護する枠組みが整えられたのです。
配偶者居住権の仕組み
配偶者居住権を活用するためには、以下のような仕組みと要件があります。
成立要件
- 相続開始(被相続人の死)時点において、配偶者がその建物に居住していたこと。
- 建物が、被相続人の単独所有または被相続人と配偶者との共有であること。被相続人以外の第三者との共有名義がある建物では対象にならないとされている。
- 配偶者を取得者とする「遺言(遺贈)」または「遺産分割協議(相続人間の合意)」または「家庭裁判所の遺産分割審判」により設定されること。つまり自動的に付与されるものではなく、配偶者自身が手続を経る必要がある。
- 登記(建物所有者と配偶者が共同して法務局に申請)を行うことで、この居住権を第三者に対しても主張できるものになる。
こららの要件を満たしていれば、配偶者居住権を活用できます。また、配偶者居住権を設定したならば、配偶者・建物所有者は法務局に以下書類等を提出し、登記することが望ましいです。登記をすることで、所有者がその建物を第三者に売却した場合でも、配偶者がその建物に住み続ける権利を第三者に対抗できます。
存続期間や消滅要件
原則として、配偶者居住権の存続期間は「配偶者の終身」です。もちろん、遺言・協議によって「〇年まで」と定めておくことも可能です。
また、消滅する要件も定められています。たとえば、配偶者が死亡する、設定された存続期間の満了、居住建物が滅失・使用不能になる、配偶者が居住権を放棄する・所有者と合意解除する、配偶者が使用方法を違反し所有者から消滅請求を受ける場合などです。
トラブルを回避するためには、成立要件だけでなく、消滅要件についても確認しておくと良いでしょう。
まとめ
配偶者居住権は、残された配偶者が「住み慣れた家に安心して暮らし続けられる」ことを目的に設けられた制度です。
相続における住居確保と財産の公平な分配を両立できる一方で、登記や消滅要件などの手続きを怠ると、権利を十分に守れないおそれもあります。制度の趣旨を理解し、専門家の助言を得ながら適切に活用することで、将来のトラブルを防ぎ、安心した暮らしを維持できるでしょう。